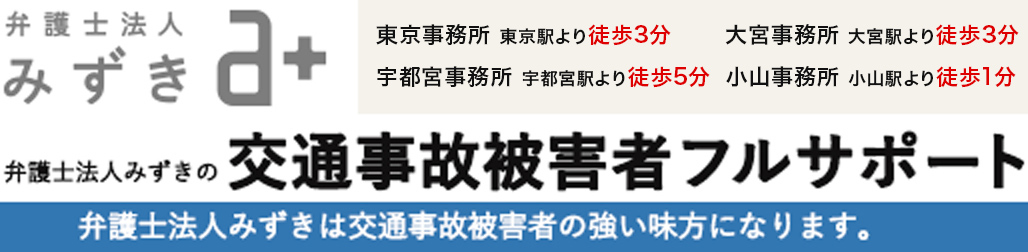顔(眼・耳・鼻・口)の後遺障害とは
眼の後遺障害
眼の後遺障害は、眼球の後遺障害と、瞼(まぶた)の後遺障害に分かれます。さらに、眼球の障害は4つ(視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害)、瞼の障害は2つ(欠損障害、運動障害)に分かれます。
1.眼球の後遺障害認定基準
<視力障害>
・第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
・第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
・第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
・第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
・第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
・第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
・第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
・第1級1号 両眼が失明したもの
<調節機能障害>
第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
<運動障害>
第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
<視野障害>
第13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
第9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
判断の分かれ道
<視力障害>
上記の等級表にある視力とは、全て矯正視力を指しています。矯正視力とは、眼鏡、コンタクトレンズや眼内レンズを使用して測定した視力のことをいいます。
つまり、メガネ、コンタクトレンズや眼内レンズをしても、上記に対応する視力が無い場合に、視力障害と認められますので注意が必要です。裸眼視力での後遺障害の認定は、矯正を行うことが不可能な場合のみ行われます。なお、ここでいう「失明」とは、以下の場合を指します。
・眼球を亡失(摘出)したもの
・明暗を弁じ得ないもの
・明暗をようやく弁ずることができる程度のもの
※明暗弁(光を点滅させ、明暗を弁別できる視力)や手動弁(掌を眼前で左右上下に動かし、動きを弁別できる能力)を含む。
<調節機能障害>
調節機能とは、対象に対してピントを合わせる機能のことをいいます。人の眼には凸レンズのような形をした水晶体という組織があり、この厚さを調節することによってピントを合わせています。水晶体の弾力性は年齢と共に衰えていくため、調節力は年齢に比例して低下します。
「著しい調節機能障害を残すもの」
調節力が通常の場合の1/2以下になる場合をいいます。
負傷したのが1眼のみであり、他眼の調節力に異常がない場合は、他眼の調節力との比較により判定します。
また、障害を負ったのが両眼である場合、又は負傷していないが他眼にも調節力の低下がみられる場合は、以下の表との比較により判定します。なお、表との比較を行う場合は、症状固定時における年齢を元に判定します。
| 年齢 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
| 調節力(D) |
9.7 |
9 |
8 |
6.3 |
5.3 |
4.4 |
3.1 |
2.2 |
1.5 |
1.4 |
1.3 |
<運動障害>
「複視」
複視とは、ひとつの物が二重に見えることをいいます。眼球は各眼3対、併せて6対の外眼筋が緊張を保つことによって正常な位置を保っています。
いずれかの外眼筋が機能しなくなる場合、麻痺性斜視となり、その外眼筋が作用する方向の眼球の動きが制限されることになります。たとえば右側へ眼球を動かす外眼筋が機能しなくなった場合、正面と左側はひとつに見えますが、右側を見たときに複視がおきます。
「複視を残すもの」
次のいずれにも該当するものをいいます。
Ⅰ 本人に自覚症状があるもの
Ⅱ 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
Ⅲ ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛で5度以上離れた位置にあることが確認できること
このヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置のずれを評価する検査方法です。
「正面視で複視を残すもの」
正面視で複視を残すものとは、ヘススクリーンテストにより、正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいい、「正面視以外で複視を残すもの」とはそれ他の場合をさします。
「著しい運動障害を残すもの」
眼球の注視野の広さが1/2以下に制限されているものをいいます。
注視野とは、頭部を固定した状態で眼球のみを動かして直視することのできる範囲をいいます。個人差がありますが、制限が無い場合は、単眼で50度、両眼で45度と言われています。
<視野障害>
視野とは、眼前の一点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいいます。
視野の測定はゴールドマン型視野計によります。
後遺障害等級認定表上の「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」とは、ゴールドマン型視野計を用いて測定した、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になる場合をいいます。なお、日本人の視野の平均値は以下の表のとおりといわれています。
| 方向 |
上 |
上外 |
外 |
外下 |
下 |
下内 |
内 |
内上 |
| 視野(V/4) |
60(55-65) |
75(70-80) |
95(90-100) |
80(75-85) |
70(65-75) |
60(50-70) |
60(50-70) |
60(50-70) |
①半盲症とは
半盲症とは、注視点を境界として、両眼の視野の右半分又は左半分が欠損する症状をいいます。視神経繊維が、視神経交叉(左右の眼かの網膜から発する視神経が交叉している部分)またはそれより後方が損傷を受けることにより生じるといわれています。
②視野狭窄とは
視野狭窄(しやきょうさく)とは、その名のとおり、視野が狭窄することを意味します。
視野狭窄には同心性視野狭窄と、不規則性視野狭窄があります。
・同心性視野狭窄
中心部分ははっきり見えるが、周辺部分が見えにくく、視野全体が狭くなるもの。
・不規則性視野狭窄
不規則に欠けて視野が狭くなるもの。
③視野変状とは
通常、視野変状というと、半盲症、視野の欠損、視野狭窄や暗点が含まれますが、ここでいう視野変状とは、視野欠損と暗点のことを指します。
2.まぶたの後遺障害認定基準
<欠損障害>
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
<運動障害>
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
判断の分かれ道
まぶたの欠損、運動障害は医師の視診と触診で判断されます。
補強資料として、写真を添付するといいでしょう。
<欠損障害>
「まぶたに著しい欠損を残すもの」
閉瞼時(まぶたを閉じた時)に各幕を完全に覆うことができない程度のもの
「まぶたの一部に欠損を残すもの」
閉瞼時に各幕を完全に覆うことはできるが、球結膜(白目の部分)が露出している程度のもの
「まつげはげを残すもの」
まつげのはえている周辺の1/2以上にわたってまつげのはげを残すもの
<運動障害>
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」
開瞼時(まぶたを開いた時)に瞳孔を完全に覆うもの、又は閉瞼時に各幕を完全に覆うことができないもの
耳の後遺障害
耳の後遺障害は、内耳等の障害と、耳殻の障害の2つがあります。内耳の障害は聴力障害、耳殻の障害は欠損障害です。
なお、内耳損傷による眩暈等の平衡機能障害については、内耳神経の障害以外にも中枢神経系の障害により症状が現れる場合も多いため、「神経系統の機能障害」として認定します。
耳の後遺障害認定基準
<聴力障害>
(両耳の聴力障害)
第11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
第10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第9級8号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第9級7号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
第7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
(1耳の聴力障害)
第14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
第11級5号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
第10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
第9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
<欠損障害>
第12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
判断の分かれ道
<聴力の障害>
聴力検査は、純音を聴き取る「純音聴力レベル」の聴力検査と、語音を聞き分ける「明瞭度」を調べる語音聴力検査の2種類があります。
①純音聴力検査
普通の人がぎりぎり聞こえるか聞こえないかの大きさの音を0dB(デシベル)とし、被験者の聴力と比較する検査です。音は空気中を伝わってくるものと、骨を伝わって内耳に直接入ってくる音の2種類があります。このため、聴力を測る場合は、気導聴力検査と骨導聴力検査の2種類を行います。
②語音聴力検査
「ア」や「カ」などの語音の聞き分けができているかにより検査を行います。この検査の結果がよくない場合、音としては聴こえるけれども相手の話している事がわからないという症状がでます。
なお、明瞭度の単位は「%」で表します。一般的に、明瞭度が50%を下回ると、補聴器を使っても効果が出にくいと言われています。
(聴力検査結果による等級別認定基準)
【両耳】
4級3号
・両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベルが80db以上であり、且つ最高明瞭度が30%以下のもの
6級3号
・両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、且つ最高明瞭度が30%以下のもの
6級4号
・1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、且つ他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
7級2号
・両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、且つ最高明瞭度が50%以下のもの
7級3号
・1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、且つ他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
9級7号
・両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、且つ最高明瞭度が70%以下のもの
9級8号
・1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、且つ他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
10級5号
・両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、且つ最高明瞭度が70%以下のもの
11級5号
・両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの
【1耳】
9級9号
・1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
10級6号
・1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
11級5号
・1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの
・1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、且つ最高明瞭度が50%以下のもの
14級3号
・1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの
<欠損障害>
「耳殻の大部分の欠損」
耳殻の軟骨部の1/2以上を欠損したものをいいます。
外貌醜状との比較
耳殻の欠損は、外貌の醜状障害にもあたりますが、この場合、後遺障害等級の「併合」はありません。
この「併合」とは、後遺障害が2つ以上残った場合、複数の異なる後遺障害等級を一つにまとめる処理になります。
複数の後遺障害等級に該当する障害が認められた場合、その中から一番重い等級を1~3等級の範囲で上の等級に上げ、「併合○級」といった表記の等級が認定されます(ただし、14級が複数の場合は、等級の上昇はなく、併合14級という表記に変わるのみです。併合にはいくつかのルールがあります。)。
耳の欠損障害の場合には、耳の欠損障害としてとらえた場合の等級と、外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級を比較し、等級が高い方のみを認定します。
たとえば、耳殻の大部分の欠損は耳の後遺障害の場合12級になりますが、醜状障害の場合は7級に該当します。この場合、7級が認定されます。
なお、耳殻の軟骨部の1/2以上の欠損に達しない場合で、「外貌に醜状を残すもの」の程度に該当する場合は、12級が認定されます。
鼻の後遺障害
鼻の後遺障害は、基準ひとつのみとなります。
鼻の後遺障害認定基準
第9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
判断の分かれ道
鼻の後遺障害として認定されるには、欠損障害と機能障害のいずれをも満たす必要があります。
①鼻を欠損
鼻の欠損とは、鼻軟骨の全部又は大部分の欠損をいいます。
②機能に著しい障害を残すもの
鼻呼吸困難又は嗅覚脱失を指します。
基準に満たない鼻の欠損障害について
鼻の欠損が鼻軟骨部の1/2に満たない場合、「外貌に醜状を残すもの」の程度に該当する場合は、醜状障害として12級が認定されます。
この場合、耳殻の欠損障害同様、等級の併合はありません。外貌醜状の場合の等級と比較して、いずれか上位の等級のみが認定されます。
ただし、鼻の欠損を外貌の醜状障害ととらえる場合において、鼻以外の顔面にも瘢痕等が存する場合は、鼻の欠損と顔面の瘢痕等で併合し等級を認定することになります。
口の後遺障害
口の後遺障害は「咀嚼障害」、「言語機能障害」そして「歯牙障害」の3つをいいます。
嚥下障害や味覚障害等については、障害の程度に応じて他の障害に準じ、相当等級として認定されます。
口の後遺障害等級認定基準
<咀嚼及び言語機能障害>
第10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
第9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
第6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
第4級2号 咀嚼及び言語の機能著しい障害を残すもの
第3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
第1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
<歯牙障害>
第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級4号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
判断の分かれ道
<咀嚼障害>
「咀嚼機能を廃したもの」
流動食以外は摂取できないもの
「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」
粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもの
「咀嚼機能に障害を残すもの」
次のいずれかが医学的に確認(不正咬合、顎関節障害等)できる場合
Ⅰ 固形食物の中に咀嚼できないものがあること
Ⅱ 固形食物の中に咀嚼が十分にできないものがあること
<言語機能障害>
私達は複数の語音を一定の序列に連結し、それに特殊な意味を付加することにより、コミュニケーションをはかっています。これを綴音(ていおん)といいます。
語音には母音と子音があり、母音は声の音であり、単独で持続して発することができますが、子音は母音とあわせて初めて声に出すことができます。
子音は4種類に分類されます。
①口唇音
ま行音 ぱ行音 ば行音 わ行音 「ふ」
②歯舌音
な行音 た行音 だ行音 ら行音 さ行音 「しゅ」 「し」 ざ行音 「じゅ」
③口蓋音
か行音 が行音 や行音 「ひ」 「にゅ」 「ぎゅ」 「ん」
④喉頭音
は行音
これらの子音のいずれか又は複数を発することができない場合、言語機能障害があると判断されます。言語機能の検査は聴覚判定です。言語聴覚士や歯科医師によって行われます。
「言語機能を廃したもの」
4種の語音の内、3種以上を発音不能のもの
「言語機能に著しい障害を残すもの」
Ⅰ 4種の語音のうち2種の発音不能のもの
Ⅱ 綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思疎通することができないもの
「言語機能に障害を残すもの」
4種の語音の内、1種の発音不能のもの
<歯牙障害>
「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」
現実に喪失、又は著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。
著しくとは、歯冠部(見えている部分)の4分の3以上を欠損していることをいいます。
交通事故で現実に喪失、欠損した歯牙だけではなく、歯科技工上必要とされ削った歯の欠損が歯冠部の4分の3以上となった場合は、その歯についても判断の対象となります。
歯牙障害における逸失利益
後遺障害の等級が認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益に応じた賠償金を請求することができます。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益の事です。労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。労働能力喪失率は14級においては5%、12級においては14%というように、等級に応じた低下率が定められています。
後遺障害の等級が認定されたとしても、保険会社から逸失利益は生じていないと主張して争われるケースがあり、外貌醜状のケースや、この歯牙障害があります。
裁判所では、歯牙障害の場合、逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料を増額するという判断をしているケースがみられます。
ただし、歯牙障害は生活上の不便だけでなく、相当の精神的苦痛が生じます。また、歯科補綴は耐用年数が証明できません。考え方によっては一時的な対症療法といえます。将来歯の痛みがひどくなり、治療が必要になる、痛みにより業務に集中できなくなるという可能性はあります。
歯牙障害により適切な賠償を求める場合には、上記のような点を医師の見解や本人の具体的な事情を元に慎重に主張立証していくことが重要になるといえます。