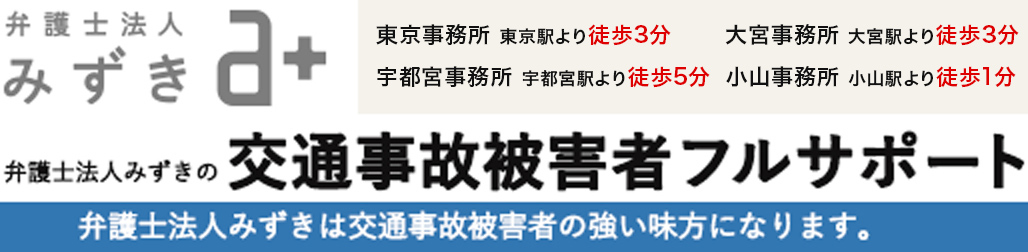怪我の治療で仕事を休まなければいけなくなったら ~休業損害について~
交通事故に遭って怪我をしてしまうと、怪我の治療のための入通院や、重傷であるため働くことができなくなったことによって、仕事を休まざるを得なくなり、生活をしていくのに必要な収入を得ることができなくなってしまうことがあります。そのような場合、交通事故の被害者は、加害者やその保険会社に休業損害として、仕事によって得られたはずの利益を請求していくことができます。
ただ、この休業損害を請求するためには、事故によって得られたはずの収入がどれくらい得られなくなったのかということをきちんと相手方に証明できなければなりません。
そこで、今回は休業損害を請求するためのポイントをご説明します。
1 休業損害を認められるのはどんな場合?
休業損害が認められるには、大前提として、被害者が交通事故発生当時に仕事に就いていなければなりません。休業損害とは、実際に仕事をして収入を得ていたにもかかわらず、事故によって得られなくなった利益を補填するものなので、事故当時実際に仕事に就いていなければ、事故があってもなくても得られる利益はないからです。
ただし、事故発生時に内定をもらっているなど、具体的に就職先が決まっているような場合には、就職を開始する予定であった日以降は、仕事をして得られたはずの利益を、休業損害として請求することができます。また、後述するように、主婦(主夫)の方は、家庭での家事が制限されたものとして、休業損害を請求することができます。
2 どこまでの範囲が休業損害として認められる?
交通事故で怪我をしたからといって、それ以降の仕事を休んだすべての期間について休業損害が認められるとは限りません。
足を骨折して動けないとか、運転手として働いている方が手首を骨折して運転できないなど、仕事に支障があってやむを得ず休業しなければならないのであれば、その期間については認められる可能性が高いですが、打撲傷など軽傷の場合に、事故の後ずっと仕事を休んでしまうと、休業の必要性がないとして、休業損害として請求しても認められる可能性は低いでしょう。
もっとも、怪我の治療のため、仕事を休んで病院に通院したような場合であれば、休業損害は問題なく認められます。なお、有給休暇を使って通院した場合、仕事を休んでも給料は支払われるので損害はないとも思えますが、事故によって怪我をしなければ通院でなく他のことに有給休暇を使えたのですから、実質的には損害が生じていると考えられるので、その日の休業損害も認められることになります。
休業損害が認められる期間については、怪我の治療が終了するまでであって、治療終了後に仕事を休んだ分については認められません。もし治療終了後にも後遺症が残ってしまい、そのために仕事に支障が出てしまうことで将来にわたって得られるはずの利益が得られなくなるような場合には、後遺障害による逸失利益の問題となり、これは休業損害とは別のものとなります。
3 休業損害はどのように計算される?
休業損害は、基本的には、1日あたりどれくらいの収入を得ていたかと、仕事を何日間休んだか、すなわち1日あたりの収入×休業日数で、計算されることになります。たとえば1日あたり1万円の収入を得ていた人が合計で10日間仕事を休まなければならなくなったのであれば、休業損害として10万円を相手方に請求することができます。
ただし、1日あたりの収入については、会社員、自営業、主婦など、業態や立場によって、計算方法が変わってきますので、単純に決まった方法で計算できるものではありません。もっとも、自賠責保険に休業損害を請求するような場合は、原則として休業1日あたり5700円の収入で計算されて、休業日数分が支払われることになります。
4 1日あたりの収入の求め方は?
3で述べたように、1日あたりの収入については、被害者の立場によって計算方法が違います。以下では、その立場ごとの計算方法をご紹介します。
(1)給与所得者
給与所得者は、事故前3か月の収入を基礎に、1日あたりの収入を求めることになります。この場合、事故前3か月の収入を90日で割るか、それとも実際に稼働していた日数で割るかで、1日あたりの収入が変わってきますので、その点については相手方との間で争いが生じる可能性がありますが、それ以外の点では争いが生じることはあまりありません。
就業予定日が決まっており、月の収入が把握しやすい会社員のほか、アルバイトやパートなどの方についても、1日あたりの収入は同じように計算することができ、事故前に働いていたシフトなどで週に何回働いていたかなどが確認できれば、休業日数も把握できますので、問題なく休業損害を請求することができると考えられます。
相手方に休業損害を請求するために必要となるものとしては、事故の前年度分の源泉徴収票と休業損害証明書という書類になります。この休業損害証明書には、被害者が事故前3か月にどのくらいの収入を得ていたかや、実際に事故のために休んだ日付を勤務先に記載してもらい、それによって1日あたりの収入や休業日数を証明することが可能となります。
(2)事業所得者
事業所得者の場合、給与所得者と異なり、勤務先というものがありませんので、休業損害証明書によって収入や休業日数を証明することができません。そのため、事業所得者については、事故の前年度の確定申告所得額と事故に遭った年の確定申告所得額を比較して、実際に減収した額を基準に休業損害を算定する方法が取られることが多いです。年度ごとに業績の変動が大きいような事情があるなど、単純に事故前年度の確定申告所得のみを基準に算定すると休業損害が著しく低くなってしまうような場合には、過去数年分の確定申告所得の平均的な所得から休業損害を算定するという方法もあります。
休業損害を請求する場合に必要な書類としては、まず事故前年、場合によっては事故前数年間の確定申告書の控えと、その添付書類(白色申告の場合は収支内訳書の控え、青色申告の場合は所得税青色申告決算書の控え)が通常要求され、確定申告書の控えに税務署の受付印がないような場合には、事故翌年の課税証明書が要求されます。
(3)会社役員
会社役員の報酬は、労務提供の対価として支払われるものと役員としての地位に基づいて支払われるものがあり、後者についてはその地位に留まる限り、休業しても支払われなくなるということがありませんので、休業損害としては認められません。
労務対価部分の報酬については、役員として実際に仕事をしたことに対して支払われるものですので、給与と同様に休業損害として認められます。もっとも、役員としての地位に基づく報酬も支払われているような場合には、両者を区別するため、会社の規模や収益、業務内容、役員の職務内容、年齢、報酬額、類似法人の役員報酬の支給状況等を参考にして、労務対価部分の報酬が全体の報酬のうちの何割に当たるのかを確定させることで、休業損害を割り出します。
(4)家事従事者(主婦(夫))
被害者が専業主婦(夫)の場合、実際には就業していないため、休業損害は発生しないとも思われます。しかし、家庭における家事も労働に当たるものとして、家事従事者としての休業損害を請求することができるというのが判例の考え方です。
家事従事者の1日あたりの収入は、女性の年間の平均賃金をもとに、それを365日(閏年の場合は366日)で割った金額で計算されます。主夫の方の場合、男性だから女性より高額な男性の平均賃金で計算されるかというと、そうではありません。なぜなら、男女の差によって家事の内容が異なるわけではないからです。なお、兼業主婦(夫)の場合、仕事で得られる1日あたりの収入と平均賃金で計算される収入のいずれを基準とすることも可能です。
休業日数については、重傷の場合はともかく、治療中に家事がまったく行えないということはありませんので、怪我によってどのくらい家事に制限が出ていたのかを割合的に考えることが多いです。たとえば、実際に通院した日については通院した分制限される割合が大きいと考え、それ以外の日については制限割合を小さく考えたり、事故直後は怪我によって家事が思うようにできないため制限割合を大きく考え、治療が進むにつれて制限割合を小さく考えるなど、考え方は様々です。
休業損害は、その計算方法次第で金額が大きく変わってくる可能性がありますので、相手方との示談交渉に当たっては、休業損害についてしっかりと理解しておく必要があります。当事務所では、交通事故の被害者の方が適正な賠償を受けられるよう、弁護士が具体的なアドバイスをするなどして、お客様をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談下さい。